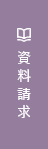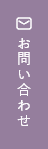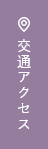学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
学修成果に係る評価
1. 単位の認定について
授業科目の単位は、履修登録をした上で授業に出席し、シラバスに示してある「評価方法」に基づく成績評価の結果により、科目責任者によって認定されます。入学前の既修得単位の認定、他の大学等における授業科目の履修等及び大学以外の教育施設等における学修の単位認定を行うことがあります。
2. 成績の評価
成績評価は S、A、B、C、D の 5 段階で行い、D評価は不合格とします。定期試験と追試験の評価基準は、100点満点の場合、S:90点以上、A:80点以上、B:70~79点、C:60~69点、D:60点未満です。シラバスに記載された到達目標をどの程度修得できているかを以下の基準で判断して評価します。再試験の評価基準は、C:60点以上、または D:59点以下のみで、S、A、B の評価はありません。
| S | 100~90点 | 到達目標を超えたレベルに達している |
| A | 89~80点 | 到達目標をほぼ達成している |
| B | 79~70点 | 到達目標は達成していないが、理解度は高い |
| C | 69~60点 | 到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達している |
| D | 59点以下 | 最低限のレベルに到達していない |
一度修得した科目の評価は取り消すことができません。
D評価となった科目の単位を取得するためにはその科目を再履修しなければなりません。
再履修とは、取得することができなかった単位を取得する必要がある場合に、次セメスター以降に改めて履修登録を行い、履修することをいいます。
D評価となった科目の単位を取得するためにはその科目を再履修しなければなりません。
再履修とは、取得することができなかった単位を取得する必要がある場合に、次セメスター以降に改めて履修登録を行い、履修することをいいます。
3. GPA 制度について
本学では、GPA(Grade Point Average)制度を導入しています。GPA 制度は、学習の質を評価する成績評価として諸外国でも用いられており、合格した科目だけでなく、不合格や履修放棄の科目も成績算出対象となるのが大きな特徴です。従って学生のみなさんは自分の履修(登録)に対して、より真剣に取り組むことが求められます。
GPA 制度の導入により、学生のみなさんが自分の目標に向かい科目履修を行なう中で、自分自身の成長をしっかり把握し、学習意欲の向上へと結びつくことを期待しています。
GPA 制度の導入により、学生のみなさんが自分の目標に向かい科目履修を行なう中で、自分自身の成長をしっかり把握し、学習意欲の向上へと結びつくことを期待しています。
①GPA の算出方法
GPA=Σ(GP×その科目の単位数)/総履修登録単位数(不合格科目含む)
GP=(TS-55)/10
TS:科目の点数
②GPAと成績の関係は以下の通りです。
GPA=Σ(GP×その科目の単位数)/総履修登録単位数(不合格科目含む)
GP=(TS-55)/10
TS:科目の点数
- 点数が60点未満になった科目はGP=0
- 再試験で合格となった科目はGP=0.5
②GPAと成績の関係は以下の通りです。
| 成績評価 | GPA |
| S(90~100点) | 3.5~4.5 |
| A(80~89点) | 2.5~3.4 |
| B(70~79点) | 1.5~2.4 |
| C(60~69点) | 0.5~1.4 |
| D(0~59点) | 0 |
修業年限及び卒業に必要な修得単位数
1. 看護学部、社会福祉学部、リハビリテーション学部
- 修業年限
大学学則第6条により、修業年限は4年としています。 - 卒業に必要な修得単位数
大学学則第39条により、以下のとおりです。
| 学部 | 学科 | 卒業に必要な単位数 |
| 看護学部 | 看護学科 | 124単位(必修109単位) |
| 社会福祉学部 |
社会福祉学科 | 125単位(必修29単位) |
| こども教育福祉学科 ※2023年度より学生募集停止 |
125単位(必修21単位) | |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 125単位(必修108単位) |
| 作業療法学科 | 125単位(必修106単位) | |
| 言語聴覚学科 | 125単位(必修107単位) | |
| 国際教育学部 | こども教育学科 | 124単位(必修25単位) |
2. 助産学専攻科
- 修業年限
助産学専攻科規則第4条により、修業年限は1年としています。 - 修了に必要な修得単位数
助産学専攻科規則第9条により、修了に必要な単位数は32単位としています。
3. 大学院
- 修業年限
大学院学則第6条により、以下のとおりとなっています。
本大学院の博士前期課程の標準修業年限は2年としています。ただし、長期在学コースの修業年限は3年としています。
本大学院の博士後期課程の標準修業年限は3年としています。ただし、長期在学コースの修業年限は4年としています。 - 修了に必要な修得単位数
大学院学則第33条により、博士前期課程の修了に必要な修得単位数は次のとおりです。
授業科目について、看護学研究科の修士論文コースにおいては32単位以上、看護学研究科の高度実践看護コースにおいては38単位以上、リハビリテーション科学研究科および社会福祉学研究科においては30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審査および最終試験に合格した者をもって修了と認定しています。
大学院学則第34条により、博士後期課程の修了に必要な修得単位数は次のとおりです。
授業科目について14単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査および最終試験に合格した者をもって修了と認定しています。
取得可能な学位
大学で取得可能な学位は大学学則第40条により以下のとおりです。
| 学部 | 学科 | 学位 |
| 看護学部 | 看護学科 | 学士(看護学) |
| 社会福祉学部 |
社会福祉学科 | 学士(社会福祉学) |
| こども教育福祉学科 ※2023年度より学生募集停止 |
学士(教育学) | |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 学士(リハビリテーション学) |
| 作業療法学科 | ||
| 言語聴覚学科 | ||
| 国際教育学部 | こども教育学科 | 学士(教育学) |
大学院で取得可能な学位は大学院学則第35条により以下のとおりです。
| 学部 | 学科 | 学位 |
| 看護学研究科 | 博士前期課程 | 修士(看護学) |
| 博士後期課程 | 博士(看護学) | |
| リハビリテーション科学研究科 | 博士前期課程 | 修士(リハビリテーション科学) |
| 博士後期課程 | 博士(リハビリテーション科学) | |
| 社会福祉学研究科 | 博士前期課程 | 修士(社会福祉学) |
| 博士後期課程 | 博士(社会福祉学) |
卒業時に取得できる国家資格
本学の特徴は、卒業後、保健医療福祉の専門職として活躍することができる登録資格や免許状または国家試験受験資格を卒業時に取得できることです。資格には、卒業要件を満たすことで取得が可能な資格と、資格取得のために履修登録を行って計画的に履修を行わなければならないものがあります。取得可能な資格は、学部により以下のとおりです。
(大学学則 第41条、助産学専攻科規則 第12条)
(大学学則 第41条、助産学専攻科規則 第12条)
| 学部 | 学科 | 資格 |
| 看護学部 | 看護学科 | 看護師国家試験受験資格 保健師国家試験受験資格 養護教諭1種免許状 |
| 社会福祉学部 |
社会福祉学科 | 社会福祉士国家試験受験資格 精神保健福祉士国家試験受験資格 介護福祉士国家試験受験資格 |
| こども教育福祉学科 ※2023年度より学生募集停止 |
保育士登録資格 幼稚園教諭1種免許状 小学校教諭1種免許状 |
|
| 学部共通 | 社会福祉主事任用資格 児童指導員任用資格 |
|
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 理学療法士国家試験受験資格 |
| 作業療法学科 | 作業療法士国家試験受験資格 | |
| 言語聴覚学科 | 言語聴覚士国家試験受験資格 | |
| 国際教育学部 | こども教育学科 | 幼稚園教諭1種免許状 小学校教諭1種免許状 保育士登録資格 社会福祉主事任用資格 児童指導員任用資格 |
| 助産学専攻科 | 助産師国家試験受験資格 受胎調節実地指導員 |
授業評価の実施状況と評価結果
本学では、全学FD委員会の取り組みとして学生による授業評価を行ない、その実施状況と評価結果を公開しています。