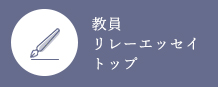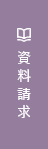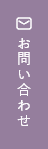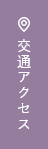「聴こえ8030運動」を知っていますか
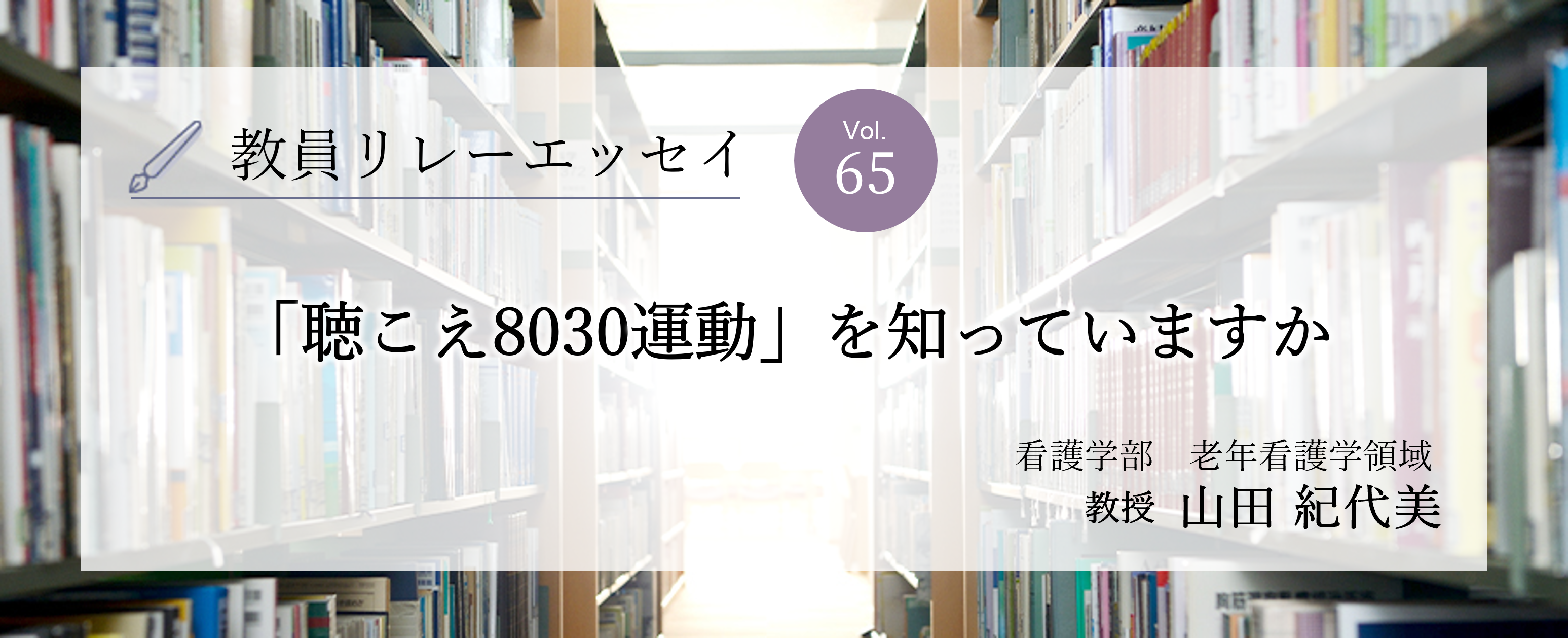
2025年11月10日更新
人間は加齢に伴い身体の機能が低下してきます。耳の聞こえも例外ではありません。2010年愛知県大府市の地域住民を対象に聴力に関する大規模な調査が行われました。それによると、25dBを超えた難聴者は65 歳以上で急峻な増加を示し、70~74 歳男性で5割、女性で 4割、75~79歳では約7割の高齢者が難聴に該当していました。聴力の低下は、コミュニケーションがうまくいかないだけで無く、抑うつ傾向や社会参加をも阻害することがわかっています。最近では、難聴と認知症の関係性も広く知られることとなり、難聴に注目が集まっています。
私は、これまで高齢者がいつまでも健康で生き生きと暮らす社会の実現を目指して様々な研究を進めてきました。中でも聴力については、通所サービスを利用する高齢者の外出や交流に関する共同研究において、外出頻度には低音の聞こえと関係があることを明らかにしました。次に、地域の介護予防事業に通う高齢者139名の聴力の実態を調査したところ、3割強で中等度以上の難聴があること、一方で聞こえの低下を自覚していない高齢者が一定程度いることが分かりました。視力は運転免許の更新時などに知ることができますが、聴力は測定の機会が少ないことがその一因かも知れません。そこで、特別な機器を用いること無く聴力の程度を知ることができるための簡易スクリーニングツールの信頼性・妥当性なども調べました。また、難聴の当事者のみならず家族が感じるコミュニケーションにおける困難などにも取り組んできました。
それらの経験を元に、現在では、高齢者自身が聞こえに対して関心をもつことができるように、ヒアリングアウェアネス(聞こえの気づき)と言う考え方を提唱し、難聴になる前から聞こえの状況を意識すること、自分自身で常に聞こえをモニターし変化への気づきを高めることを目指しています。この第一歩として地域の正常な聴力の高齢者にインタビューを行ったところ、難聴に関する知識はある程度持ち合わせているものの、加齢性難聴への関心の程度は低く、特に補聴器の利用については自分事として考えることもなく、できたら補聴器は避けたいといった気持ちが明らかとなっています。この結果から次なる研究は補聴器へのイメージの転換を目指して装着者の肯定的な体験を調査する予定でいます。
折しも、一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が「聴こえ8030運動」を展開しています。これは、80歳で30dBの聴力を保つ国民啓発運動です。この様な追い風の中、私も引き続き、高齢者が確かな聴力による会話を通して社会参加ができるように、難聴の研究に精力的に取り組んでいきたいと思っています。
私は、これまで高齢者がいつまでも健康で生き生きと暮らす社会の実現を目指して様々な研究を進めてきました。中でも聴力については、通所サービスを利用する高齢者の外出や交流に関する共同研究において、外出頻度には低音の聞こえと関係があることを明らかにしました。次に、地域の介護予防事業に通う高齢者139名の聴力の実態を調査したところ、3割強で中等度以上の難聴があること、一方で聞こえの低下を自覚していない高齢者が一定程度いることが分かりました。視力は運転免許の更新時などに知ることができますが、聴力は測定の機会が少ないことがその一因かも知れません。そこで、特別な機器を用いること無く聴力の程度を知ることができるための簡易スクリーニングツールの信頼性・妥当性なども調べました。また、難聴の当事者のみならず家族が感じるコミュニケーションにおける困難などにも取り組んできました。
それらの経験を元に、現在では、高齢者自身が聞こえに対して関心をもつことができるように、ヒアリングアウェアネス(聞こえの気づき)と言う考え方を提唱し、難聴になる前から聞こえの状況を意識すること、自分自身で常に聞こえをモニターし変化への気づきを高めることを目指しています。この第一歩として地域の正常な聴力の高齢者にインタビューを行ったところ、難聴に関する知識はある程度持ち合わせているものの、加齢性難聴への関心の程度は低く、特に補聴器の利用については自分事として考えることもなく、できたら補聴器は避けたいといった気持ちが明らかとなっています。この結果から次なる研究は補聴器へのイメージの転換を目指して装着者の肯定的な体験を調査する予定でいます。
折しも、一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が「聴こえ8030運動」を展開しています。これは、80歳で30dBの聴力を保つ国民啓発運動です。この様な追い風の中、私も引き続き、高齢者が確かな聴力による会話を通して社会参加ができるように、難聴の研究に精力的に取り組んでいきたいと思っています。
関連リンク
-

山田 紀代美 教授についての情報はこちら