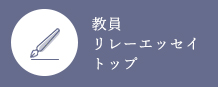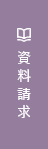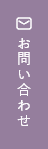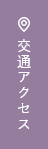汗をかくほど、強くなる。暑熱順化という“夏のリハビリ”
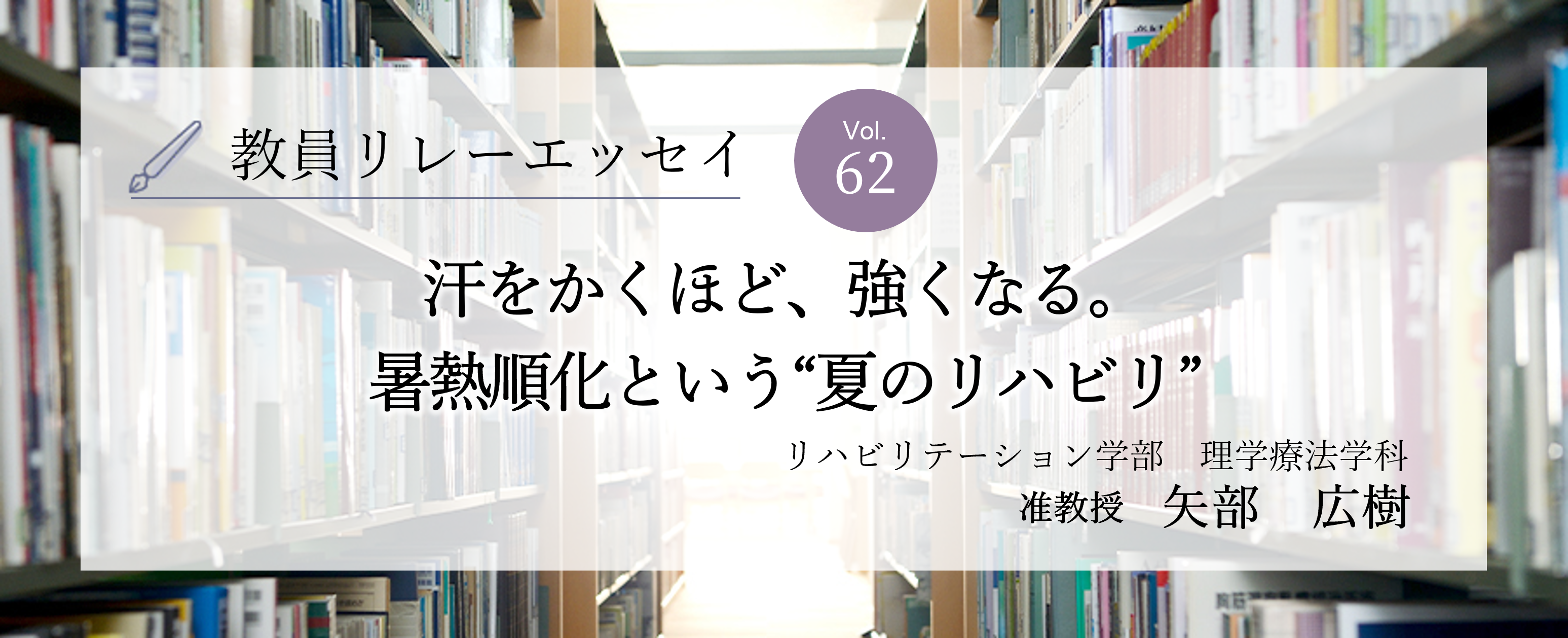
2025年8月10日更新
暑い日々が続いています。
『学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き』によれば、暑さ指数(WBGT※)が25〜28(参考気温28〜31℃)では「厳重警戒:激しい運動は中止」、31以上(参考気温35℃以上)では「運動は原則中止」とされています。気温が高い中での運動は、平時よりも多くのエネルギーを消費し、体内の熱をうまく放散できないおそれがあるため、熱中症対策が極めて重要です。
先日実家に帰省した際、日中の暑い時間帯に畑仕事をしていた父(おじいちゃん)に対し、母(おばあちゃん)が烈火のごとく怒っていました。「熱中症で天国行きになるよ!」と強く訴える母に対し、父はどこ吹く風のような涼しい顔をしています。私の知る限り「畑仕事における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」は存在しませんが、小学校でプールの授業が暑さのため中止になる中、炎天下での畑作業が安全とは到底思えません。しかし一方で、ふと疑問も浮かびます。なぜ父は炎天下でも平然と作業ができるのでしょうか。
「暑熱順化(しょねつじゅんか)」という言葉をご存じでしょうか。暑熱順化とは、身体を徐々に暑さに慣れさせることで、熱中症のリスクを軽減する生理的適応の一つです。人間の体は、発汗や皮膚の毛細血管の血流を増やすことにより、体内の熱を放散し体温を調節します。これらの反応はすべて自律神経の制御下にあり、暑さに繰り返し曝露されることで、この放熱反応が「鍛えられ」、より効率的に体温調節ができるようになるのです。父は春先のまだ気温がそれほど高くない時期から、ずっと畑仕事を続けていました。炎天下でも作業をやめずにいたことで、父の身体は自然と暑熱順化を獲得していったのでしょう。空調の効いた室内で過ごす時間が多く、暑さへの耐性が低い私とは大違いです。
暑熱順化における「自律神経反応と熱放散能力を鍛える」という考え方は、「自らの体をより良く作り替える」というリハビリテーションの根本理念にも通じるものがあります。心も体も、そして暑さに対する反応すらも、鍛えることで強くなるのです。母の怒りに満ちた「熱中症対策」に加えて、父が図らずも身につけた「暑熱順化による体温調節能力」。天国行きはご勘弁願いたいけれど、畑に立つ父の背中には、どうやら生きる知恵が詰まっているようです。
※暑さ指数(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)とは、気温、湿度、輻射熱、風などを加味して算出される熱中症リスクの指標です。
『学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き』によれば、暑さ指数(WBGT※)が25〜28(参考気温28〜31℃)では「厳重警戒:激しい運動は中止」、31以上(参考気温35℃以上)では「運動は原則中止」とされています。気温が高い中での運動は、平時よりも多くのエネルギーを消費し、体内の熱をうまく放散できないおそれがあるため、熱中症対策が極めて重要です。
先日実家に帰省した際、日中の暑い時間帯に畑仕事をしていた父(おじいちゃん)に対し、母(おばあちゃん)が烈火のごとく怒っていました。「熱中症で天国行きになるよ!」と強く訴える母に対し、父はどこ吹く風のような涼しい顔をしています。私の知る限り「畑仕事における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」は存在しませんが、小学校でプールの授業が暑さのため中止になる中、炎天下での畑作業が安全とは到底思えません。しかし一方で、ふと疑問も浮かびます。なぜ父は炎天下でも平然と作業ができるのでしょうか。
「暑熱順化(しょねつじゅんか)」という言葉をご存じでしょうか。暑熱順化とは、身体を徐々に暑さに慣れさせることで、熱中症のリスクを軽減する生理的適応の一つです。人間の体は、発汗や皮膚の毛細血管の血流を増やすことにより、体内の熱を放散し体温を調節します。これらの反応はすべて自律神経の制御下にあり、暑さに繰り返し曝露されることで、この放熱反応が「鍛えられ」、より効率的に体温調節ができるようになるのです。父は春先のまだ気温がそれほど高くない時期から、ずっと畑仕事を続けていました。炎天下でも作業をやめずにいたことで、父の身体は自然と暑熱順化を獲得していったのでしょう。空調の効いた室内で過ごす時間が多く、暑さへの耐性が低い私とは大違いです。
暑熱順化における「自律神経反応と熱放散能力を鍛える」という考え方は、「自らの体をより良く作り替える」というリハビリテーションの根本理念にも通じるものがあります。心も体も、そして暑さに対する反応すらも、鍛えることで強くなるのです。母の怒りに満ちた「熱中症対策」に加えて、父が図らずも身につけた「暑熱順化による体温調節能力」。天国行きはご勘弁願いたいけれど、畑に立つ父の背中には、どうやら生きる知恵が詰まっているようです。
※暑さ指数(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)とは、気温、湿度、輻射熱、風などを加味して算出される熱中症リスクの指標です。
関連リンク
-

矢部 広樹 准教授についての情報はこちら