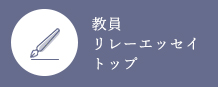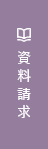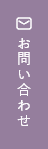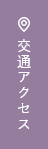音楽がひらく、子どもの“こころの力”
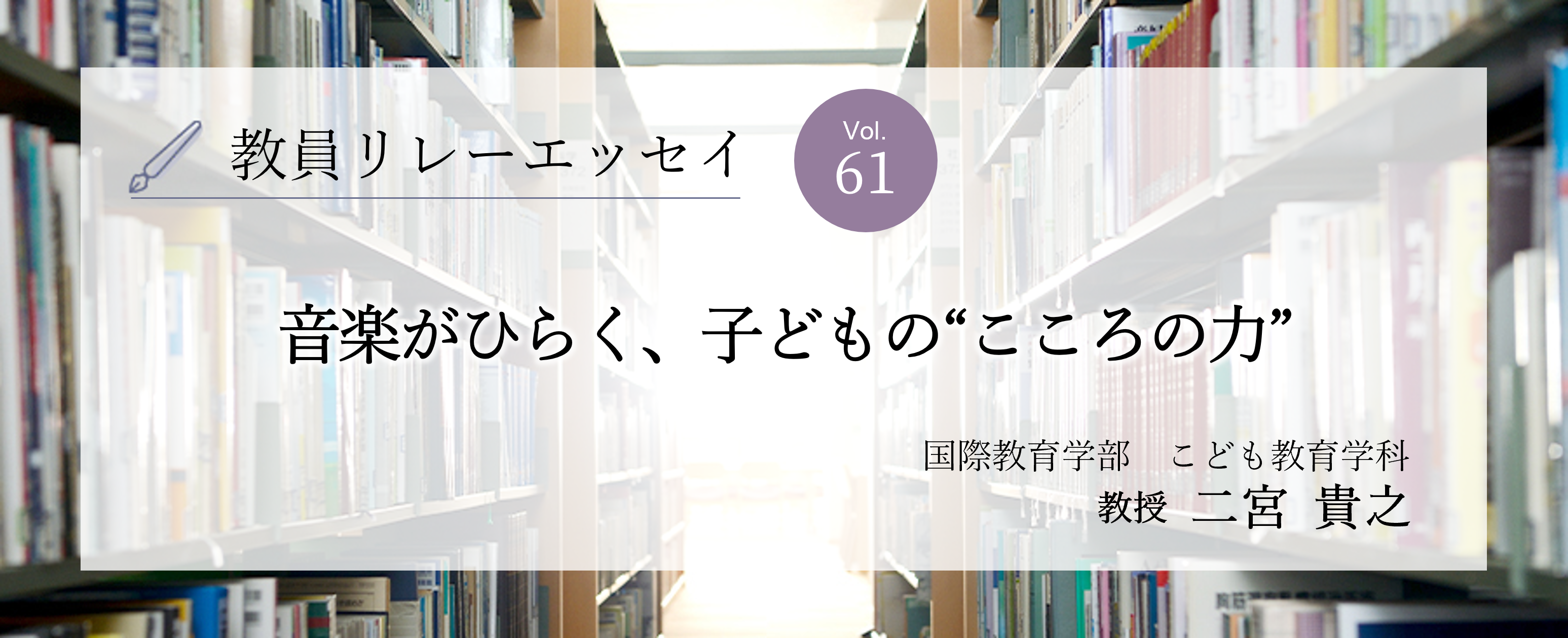
2025年7月10日更新
「音楽を学ぶと心が豊かになる」これはよく耳にする言葉ですが、最近の教育研究では、この「心の豊かさ」に科学的な裏付けが加わりつつあります。OECD(経済協力開発機構)などが注目する「非認知能力」は、学力テストには表れにくい、忍耐力・協調性・自己肯定感・感情のコントロールなど、人生を豊かに生きるための「こころの力」とも言えます。
私はこれまで大学で声楽、合唱、リトミック、器楽、合奏、音楽科指導法などを教える傍ら、海外でも音楽ワークショップを開催してきました。実践の中で実感するのは、音楽活動が子どもたちの非認知能力の発達に深く関わっているということです。たとえば、リトミックでは音の変化に体を合わせる中で集中力や柔軟性が育ちますし、わらべうたや歌唱では、お互いを聴き合う力や、協力しながら達成する喜びを経験します。
特に印象に残っているのは、海外の保育者や幼児との音楽ワークショップで、「子どもたちは楽譜を読むより先に“直感的に他者と響き合う”」という場面です。音楽は、言葉が通じなくても心がつながる不思議な力を持っています。だからこそ、音楽は国や文化を越えた教育資源でもあるのです。
日本の教育現場でも、これからは非認知能力を育てる視点がますます重要になります。音楽教育はそのための強力な手段です。単に「上手に歌える」「楽譜が読める」だけでなく、「音を通して他者と関われる」「自分を素直に表現できる」ことにこそ、音楽の本質的な価値があります。
今後は、地域の皆さまとも連携し、模擬授業や音楽体験の場などを通じて、こうした音楽の魅力や力を広く伝えていきたいと考えています。「音楽ってこんなに面白くて、深いんだ」と思っていただけるような場を、共に創っていけたら幸いです。
私はこれまで大学で声楽、合唱、リトミック、器楽、合奏、音楽科指導法などを教える傍ら、海外でも音楽ワークショップを開催してきました。実践の中で実感するのは、音楽活動が子どもたちの非認知能力の発達に深く関わっているということです。たとえば、リトミックでは音の変化に体を合わせる中で集中力や柔軟性が育ちますし、わらべうたや歌唱では、お互いを聴き合う力や、協力しながら達成する喜びを経験します。
特に印象に残っているのは、海外の保育者や幼児との音楽ワークショップで、「子どもたちは楽譜を読むより先に“直感的に他者と響き合う”」という場面です。音楽は、言葉が通じなくても心がつながる不思議な力を持っています。だからこそ、音楽は国や文化を越えた教育資源でもあるのです。
日本の教育現場でも、これからは非認知能力を育てる視点がますます重要になります。音楽教育はそのための強力な手段です。単に「上手に歌える」「楽譜が読める」だけでなく、「音を通して他者と関われる」「自分を素直に表現できる」ことにこそ、音楽の本質的な価値があります。
今後は、地域の皆さまとも連携し、模擬授業や音楽体験の場などを通じて、こうした音楽の魅力や力を広く伝えていきたいと考えています。「音楽ってこんなに面白くて、深いんだ」と思っていただけるような場を、共に創っていけたら幸いです。
関連リンク
-

二宮 貴之 教授についての情報はこちら