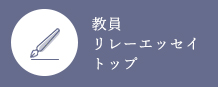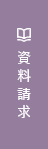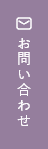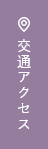異なる経路、同じ根 ― 神経メカニズムから探る吃音の本質
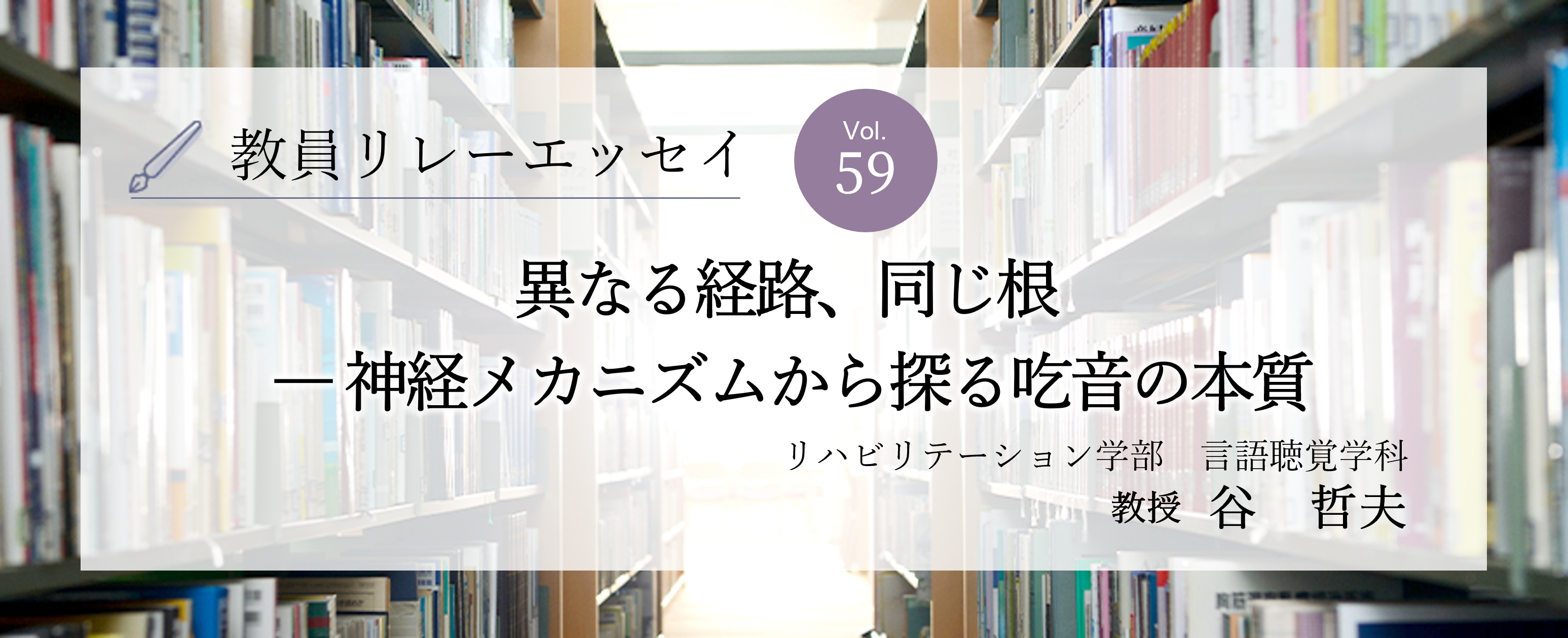
2025年5月10日更新
吃音は一般に、「発達性吃音」と「神経原性吃音」という二つのタイプに分類される。前者は言語発達の過程で自然に現れ、後者は脳損傷などの明確な医学的原因を伴って発症します。このような違いから、両者は従来、異なる現象として理解され、別々の枠組みで評価され、支援されてきました。
しかし、私はこうした分類的理解に一石を投じようと試みています。私が着目しているのは、「どのように発症したか」ではなく、「なぜ吃音が生じるのか」という根本的なメカニズムです。私の仮説は明確です。発達性吃音も神経原性吃音も、背景には共通して「神経活動の異常」が存在するという点で、本質的に同質の現象ではないかということです。
発達性吃音は、脳の発達段階で何らかの神経ネットワークの調整不全が起こることで、音声の生成や運動制御に齟齬をきたすとされています。一方、神経原性吃音は、すでに構築された神経回路が脳損傷などによって損なわれ、同様の運動制御の障害が生じます。発症のタイミングや外見上の症状には差があるものの、根底にあるのは「神経系の調整機能の破綻」であり、この点において両者は驚くほど類似しています。
この視点に立てば、吃音を年齢や発症要因によって区別するよりも、神経生理学的な共通性に着目して理解・支援を考える方が合理的であるといえます。たとえば、運動制御に関わる脳領域――前頭葉、運動皮質、基底核、補足運動野など――における活動異常は、発達性・神経原性のいずれの吃音にも報告されており、これが発話の流暢さに直接的な影響を及ぼしていると考えられるのです。
私はこのような神経科学的視座に立つことで、吃音に対するより本質的な理解と、効果的な支援方法の構築が可能になると考えています。発達性吃音を「子ども特有の一過性の現象」として扱うのではなく、神経原性吃音との共通メカニズムを視野に入れることで、より精緻で包括的な介入の道が開けると信じています。
吃音とは、単なる「ことばのつかえ」ではなく、脳の微細な働きのずれが音声行動に現れた結果であり、その意味で、発達性も神経原性も「異なる経路をたどって現れる同じ神経現象」なのではないか。私の研究は、この問いに対して神経科学と教育学の両側面からアプローチし、吃音理解の新たな地平を切り拓こうと試みているのです。
しかし、私はこうした分類的理解に一石を投じようと試みています。私が着目しているのは、「どのように発症したか」ではなく、「なぜ吃音が生じるのか」という根本的なメカニズムです。私の仮説は明確です。発達性吃音も神経原性吃音も、背景には共通して「神経活動の異常」が存在するという点で、本質的に同質の現象ではないかということです。
発達性吃音は、脳の発達段階で何らかの神経ネットワークの調整不全が起こることで、音声の生成や運動制御に齟齬をきたすとされています。一方、神経原性吃音は、すでに構築された神経回路が脳損傷などによって損なわれ、同様の運動制御の障害が生じます。発症のタイミングや外見上の症状には差があるものの、根底にあるのは「神経系の調整機能の破綻」であり、この点において両者は驚くほど類似しています。
この視点に立てば、吃音を年齢や発症要因によって区別するよりも、神経生理学的な共通性に着目して理解・支援を考える方が合理的であるといえます。たとえば、運動制御に関わる脳領域――前頭葉、運動皮質、基底核、補足運動野など――における活動異常は、発達性・神経原性のいずれの吃音にも報告されており、これが発話の流暢さに直接的な影響を及ぼしていると考えられるのです。
私はこのような神経科学的視座に立つことで、吃音に対するより本質的な理解と、効果的な支援方法の構築が可能になると考えています。発達性吃音を「子ども特有の一過性の現象」として扱うのではなく、神経原性吃音との共通メカニズムを視野に入れることで、より精緻で包括的な介入の道が開けると信じています。
吃音とは、単なる「ことばのつかえ」ではなく、脳の微細な働きのずれが音声行動に現れた結果であり、その意味で、発達性も神経原性も「異なる経路をたどって現れる同じ神経現象」なのではないか。私の研究は、この問いに対して神経科学と教育学の両側面からアプローチし、吃音理解の新たな地平を切り拓こうと試みているのです。
関連リンク
-
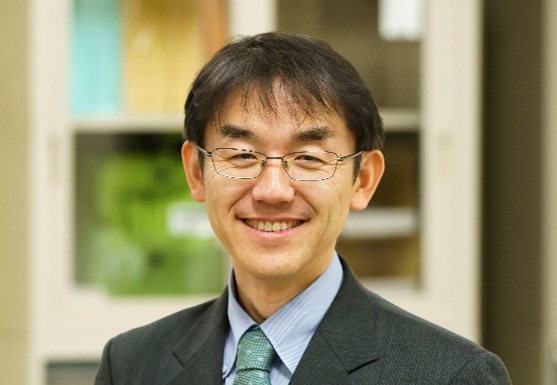
谷 哲夫 教授についての情報はこちら