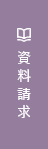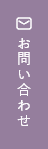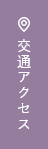【大学・高校連携教育】聖隷クリストファー高校で「がん教育」講演を実施 — 看護学部・大石教員が健康長寿のための生活習慣を伝える
聖隷クリストファー大学 看護学部 成人看護学領域の大石ふみ子教授が、聖隷クリストファー高校の生徒を対象に「がんについて学ぶ」をテーマにした講演を行いました。
この講演は、生徒の皆さんに「健康で長生きをしてほしい」という願いのもと、長寿国となった日本で最大の死因となっている「がん(悪性新生物)」について正しく理解し、若い頃から対策を講じることの重要性を伝える目的で開催されました。
大石教授は、まず平均寿命と「健康寿命」の違いを紹介し、ただ長生きするだけでなく、健康に生活できる期間を伸ばすことの大切さを強調しました。そして、日本人の「やまい」が結核などの感染症から、長年の習慣が引き起こす生活習慣病へと変化し、その代表的なものが「がん」であることを説明しました。
講演では、がんが「体の細胞分裂の際に起こる変異」から生じることや、異常な細胞が修復されずに増えることでかたまりとなる仕組みを解説。その上で、がんの原因は、生活習慣、細菌・ウイルス、遺伝的要因、そして不明のものに分類されることを示しました。
特に、自分で気をつけることができる生活習慣として、以下の「望ましい生活習慣」を挙げ、がんのリスクを減らすことができると訴えました。
また、がんの予防と並行して、早期発見・早期治療が非常に重要であるとし、「早期がんであれば9割の人が治る」というデータを示しながら、定期的ながん検診の受診を推奨しました。
大石教授は最後に、「細胞の変異は常に起こっており、がんになるには長い時間をかけるため、対策は年をとってからでは遅い」と締めくくり、高校生という早い段階から望ましい生活習慣を身につけることが、将来の元気な長生きにつながるというメッセージを力強く伝えました。
本学では、今後も地域や連携校の健康教育に貢献し、次世代を担う若者の健康意識向上を支援してまいります。
この講演は、生徒の皆さんに「健康で長生きをしてほしい」という願いのもと、長寿国となった日本で最大の死因となっている「がん(悪性新生物)」について正しく理解し、若い頃から対策を講じることの重要性を伝える目的で開催されました。
大石教授は、まず平均寿命と「健康寿命」の違いを紹介し、ただ長生きするだけでなく、健康に生活できる期間を伸ばすことの大切さを強調しました。そして、日本人の「やまい」が結核などの感染症から、長年の習慣が引き起こす生活習慣病へと変化し、その代表的なものが「がん」であることを説明しました。
講演では、がんが「体の細胞分裂の際に起こる変異」から生じることや、異常な細胞が修復されずに増えることでかたまりとなる仕組みを解説。その上で、がんの原因は、生活習慣、細菌・ウイルス、遺伝的要因、そして不明のものに分類されることを示しました。
特に、自分で気をつけることができる生活習慣として、以下の「望ましい生活習慣」を挙げ、がんのリスクを減らすことができると訴えました。
- たばこを吸わない
- バランスのよい食事
- お酒を飲みすぎない
- 適度な運動
- 適正体重の維持
また、がんの予防と並行して、早期発見・早期治療が非常に重要であるとし、「早期がんであれば9割の人が治る」というデータを示しながら、定期的ながん検診の受診を推奨しました。
大石教授は最後に、「細胞の変異は常に起こっており、がんになるには長い時間をかけるため、対策は年をとってからでは遅い」と締めくくり、高校生という早い段階から望ましい生活習慣を身につけることが、将来の元気な長生きにつながるというメッセージを力強く伝えました。
本学では、今後も地域や連携校の健康教育に貢献し、次世代を担う若者の健康意識向上を支援してまいります。